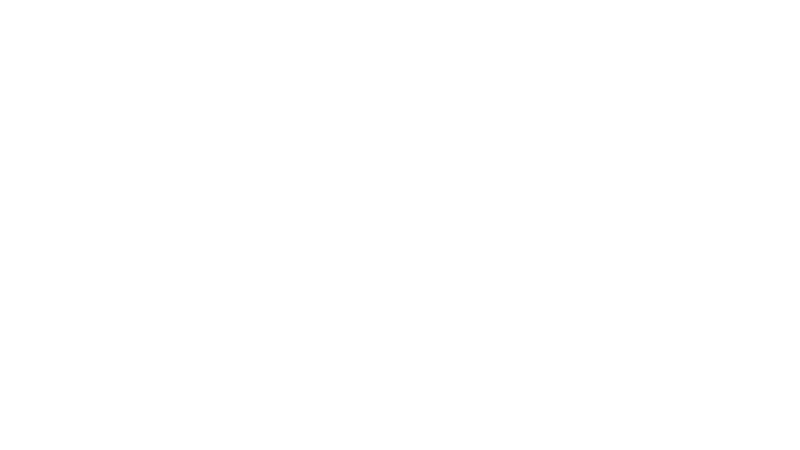挑戦する研究者へ
夢や未知の領域に挑むことは、時に勇気が必要です。先端技術―3Dバイオプリンティングの分野にあっても将来性や興味はあるものの、専門外なので難しいのではないか、未経験だからできるかどうか分からないといった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、3Dバイオプリンティングに関心のある方々に向けて、九州情報大学 経営情報学部情報ネットワーク学科の荒平高章准教授にお話を伺いました。

手作業による実験:細胞密度の均一性に課題
荒平先生は、材料の力学的強度などを検討するバイオメカニクス分野で研究をしていらっしゃいます。特に骨・軟骨細胞に使用する材料について、生体内移植を前提として、材料レベル、細胞を含め組織化させたレベルの両方から検討をされています。
荒平先生は、学生の頃からスポンジのような多孔体のコラーゲンを用いて細胞を培養し、研究をされていましたが、細胞密度の均一性の確保に課題を感じていました。特に、特定の方向から細胞を播種すると細胞の分布が偏った状態で増殖してしまい、正確な実験結果が得られない状況でした。細胞の接着性を向上させる分子構造といった材料設計からのアプローチではなく、先生の専門である物理的・構造的な改善方法を探していました。 バイオ3Dプリンタは細胞と足場材を混ぜて吐出(プリント)するので、このような課題の解決策となり、均一な細胞分布が得られる、つまり均一な組織ができるのでは、と考え、バイオ3Dプリンタの検討を始めました。
バイオ3Dプリンタにはいくつか選択肢がありますが、複数のノズルで異なる細胞やマテリアルを使い分けられるセルインクのプリンタに魅力を感じ、さらに関心を高めたのは、骨細胞用の『バイオインク※』の存在でした。
当時、ここまで充実したバイオインクのラインナップを提供していたメーカーは日本には少なかったこと、また、複数のマテリアルをプリントし分けるプリンタであったことが導入の決め手になったとおっしゃいます。
※バイオプリント用のマテリアルのこと。細胞の足場材として機能する生体適合性のあるハイドロゲル。
第一印象は「すごくコンパクト!」
INKREDIBLEを初めて見た時の印象は、そのコンパクトさでした。従来の樹脂系3Dプリンタや、実験室にある装置のイメージと異なるコンパクトなデザインやその汎用性から、研究展開の可能性を感じたと語ります。
特に、バイオインクの濃度や組成を変え、それをマルチノズルでサンドイッチのような層状構造に積層できるため、将来的にも汎用性が高く、材料のメカニクスを研究されている先生の最終的な目的に合致したと語ります。
装置のトラブルが発生した際にも、サポートチームの迅速な対応により、現在まで問題なく稼働しているとのことです。
学生たちの研究への姿勢にも変化が

先生の研究以外にも、学内の情報系の学生によるバイオ3Dプリンタの活用が増えているとのことです。特にコンピューターサイエンスや人工知能のメディカル分野への応用や、プログラムによるデータ分析、メカニクス分野での活用、皮膚のようなヒト組織の作製などを検討している学生の方々にも使われています。
バイオ3Dプリンタを使用する際、設計したものをプリントしたものと、実際のサイズが異なるなど、想定していた形状との誤差があることが課題でしたが、汎用的なガイドラインを学生同士で自主的に作るという、これまで見られなかった協力体制が構築され、コミュニティ力の強化やノウハウの共有により、学生間でもバイオプリンタの知識が広まっています。
バイオ3Dプリンタの導入によって、学生間の交流が増えたことは嬉しいポイントでした。
現在は実験も順調に進んでおり、論文発表の準備を進めていらっしゃいます。
一人でも多くの人に使って欲しい
バイオ3Dプリンタを使いこなすには、使うインクの種類や濃度によって、想定通りのモデルを作製するためにはノズルから吐出する際の圧力制御などの微調整が必要ですが、手動で押し出していた頃に比べると、作業効率や精度は向上したとのことです。また、INKREDIBLEは、純正のマテリアルでなくともプリントできるため、実験室で独自に調整したマテリアルをプリントされています。3Dプリンタの知識や経験が少ない研究者でも使いやすいので、これから導入しようとしている人や、導入へのハードルを感じている研究者の方や学生の方にも安心してもらいたい、と荒平先生はおっしゃいます。
「3Dプリンタは、自分で考えて作ったものが造形できるので、学習体験として非常に良いツールだと思う。特にバイオ3Dプリンタは、生体・人体に関わってくるので、これまで人体について意識していなかった人でも、自分がデザインしたものが、病気で苦しんでいる人の役に立ち、新たな医学的知見の発見に貢献できるなど、将来医療や薬学といった分野に貢献できるという点で、夢のある製品です。」