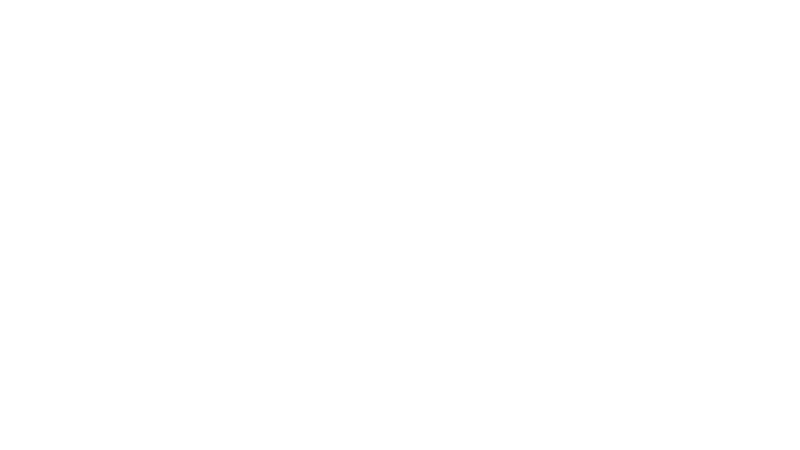GelMAを使ったバイオフィルムのバイオプリント
マイクロバイオーム研究の推進
無数の微生物が繁殖し、相互作用している微生物学の世界では、バイオフィルムが私たちの健康に重大な影響を及ぼす重要な要素となることが明らかになりました。バイオフィルムは慢性呼吸器感染症の原因となり、整形外科手術や心臓手術の後には大きな問題になります。米国だけでも280万人以上の抗生物質耐性感染症が発生し、35,000人が死亡しています(アメリカ疾病予防管理センター(CDC)より)。そのため、臨床医や微生物学者にとって、大きな課題となっています。
バイオフィルムが明かす新たな世界
従来、細菌は単細胞生物として研究され、実験室では細胞の均質性が得られる通気フラスコによる培養が主流でした。しかし、細菌は分散した状態の単一細胞であるという従来の理解は、バイオフィルムの発見によって覆されました。
バイオフィルムとは、表面に付着した自己生産ポリマーマトリックス内で組織化された、複数の細菌からなる3次元的な細胞集団(凝集体)です。細菌がプランクトン(遊泳)状態にある感染症では、抗菌剤による治療が有効ですが、バイオフィルムが形成されると、耐性は1000倍にも増加し、抗菌剤が効かなくなり、場合によっては手術などの侵襲的な治療が必要となります。
カロリンスカ研究所のFerdinand Xiankeng Choong教授は、このような複雑な多細胞構造に着目しました。
地球上のほとんどの細菌がバイオフィルム内に生息しているにもかかわらず、抗生物質の選択と新たな抗生物質の開発に関する既存のアプローチは、主に浮遊状態の細菌を対象とした抗生物質感受性試験(AST)によって行われています。これは、ASTによって決定される投与量や治療法が、バイオフィルム関連感染症を効果的に治療する可能性が低いことを示しています。
この気づきは、Choong先生の心に深い疑問を呼び起こしました:
「細菌を研究するための既存のテストや方法論に根本的な欠陥があるとしたら?」
この問題に着想を得たカロリンスカ研究所のチームは、バイオフィルムに特化し、細菌の種類に関係なく、広く適用できるASTの開発に着手しました。そのためには、まずバイオフィルム形成の複雑なプロセスを包括的に理解する必要がありました。

Ferdinand Xiankeng Choong教授は、カロリンスカ研究所統合医工学科学推進センター(AIMES)の科学者で、微生物学とバイオセンサー開発に学際的な関心を寄せています。
バイオプリンティング: バイオフィルムを研究する新たなツール
Choong先生は、バイオプリンティングのような新しい技術を活用する必要性を認識していました。研究チームは、従来の方法ではなく、GelMA(ゼラチン・メタクリレート)というバイオインクを細菌の培地として使用し、3Dバイオプリンティングによる種菌(細菌・微生物を含む液体)の試用を検討しました。
従来の実験では、研究者は培地に接種菌を一滴程加えます。細菌のコロニー化(バイオフィルムの発生)が始まると、目のような丸い形が形成されます。コロニーの拡大が進むと細菌は菌体外物質を多量に分泌し増殖していくため、密度を緩和する必要があります。そのため、コロニーは唯一のスペースである上方に折り重なり、最終的にざらざらした見た目になります。
「もしこの表面が圧力に関係しているのであれば、培養液の導入方法を変えることで、全く異なるコロニー形態が得られるかもしれない。従来のバイオフィルムの増殖には、表面に広がる液体培地が必要だったため、このような側面はほとんど研究されてこなかったのです」とChoong教授は話します。
研究チームは、コロニー形態の背後にあるメカニズムを理解する必要があったため、バイオプリンティングを研究に取り入れることにしました。
GelMAを使った細菌のバイオプリンティング
ハイドロゲルの型破りな利用法
従来ハイドロゲルは抗菌剤を保持するために使用されていましたが、Choong教授と研究チームは、この従来の方法とは全く対照的な方法、つまり、細菌を培養するためにハイドロゲルを使用する、という可能性を考えました。
細菌はコラーゲンを豊富に含む結合組織などといった宿主の細胞外物質を取り込んでバイオフィルムを形成します。そのため、研究ではコラーゲン由来の天然タンパク質であるGelMAが細菌の培地として使用されました。
この方法は、GelMAハイドロゲルの本来の使い方ではないため、研究チームはいくつもの課題に直面しました。まず、細菌の性質上、紫外線による硬化や、塩類による架橋ができませんでした。さらに、3次元モデルを硬化させると、細菌がモデル構造物内を移動することができなくなり、バイオフィルムの形成が完全に妨げられる可能性がありました。そこでGelMAの形態学的特性を利用し、マテリアルの硬化はせずに、プリントした構造物の形状維持を可能にしました。
また、プリントしたゲルの質量と体積の間に強い相関関係を確立し、実験で使用するゲルの体積を正確に推定・制御することにも成功しました。これは、バイオプリンティング技術を微生物に応用するための重要な第一歩となりました。
「バイオプリンティングの導入により、新たな挑戦や未解決の疑問がもたらされ、新しい研究分野への道が開きました。」
バイオプリンティングの導入後に得られたバイオフィルムの再定義
研究チームは、GelMAで細菌をバイオプリントすることにより、植え付けた細菌の特異的形状や表面積、表面特性を制御することができるようになりました。この新しいアプローチにより、バイオフィルム形成に関する従来の理解が覆され、コロニーの形態に関する新たな知見が得られました。
この研究で最も興味深い発見のひとつは、細菌を液滴に接種したときです。細胞外マトリックスの大部分は、液滴の中心部よりも側端に形成されました。この実験結果は、「形成されるバイオフィルムの量はコロニーの形成期間によって異なり、液滴の中心部で最も多くなる」という予想に反するものでした。
研究チームは、この現象をさらに調べるため、中心部に無菌の円形構造物を3Dプリントして作製しました。しかし、この円の内側での細菌増殖は全く見られませんでした。細菌は、円外部の存在を感知し、その方向に増殖することが有利ではないことを理解していたのです。
さらに、バイオフィルムが産生する細胞外マトリックスの量は、隣接する細胞の数とその角度に影響されることがわかりました。角度が大きいほどマトリックスの生成量は多くなり、角度が小さいほどマトリックスの生成量は少なくなりました。
細菌のプリント手順
「プロセスそのものはとても簡単です」。
まず、GelMAを可溶化させます。次にバイオインクに細菌を加え、温度制御可能なプリントヘッドに素早くセットします。続いてBIO X6を使い、完全な円、中が空洞になった円や三角形など、さまざまな幾何学的形状を増殖培地に直接プリントします。その後、インキュベーターで培養します。
「BIO X6は非常に使いやすいバイオプリンタです。HEPAフィルターや殺菌ランプ(UV-C)、垂直気流型の自動開閉ドアが搭載されており、安全キャビネットと同様の無菌環境を作り出すため、細菌を扱う際の安全規制に適しています。BIO X6を使用することで、コンタミネーションを防ぎ、プリンタから安全キャビネットにシャーレを移動する時間を節約することもできました。プリントヘッドには保温キャップが付いているので、GelMAのような温度感受性の高いバイオインクのプリントも可能にします」 – とAIMESのポスドク研究員、Sivakoti Sangabathuni博士は話します。
CELLINKとの提携について
「学術界と産業界のパートナーシップは、多様な専門知識と視点をもたらしてくれます。
CELLINKをパートナーとして迎えたことは、我々の研究にとって非常に価値のあることでした。同社から提供された具体的な回答、明確に定義された資料や実験データにより、信頼性の高い結果を得ることができました。
CELLINKの品質保証は、特に細菌のようなダイナミックな存在を研究する際、我々の研究の軸となりました」。– Choong教授
バイオプリンティングによるバイオフィルム:医療・産業分野での活用
3D環境でバイオフィルムを形成できたことは、Choong教授のグループにとってまだ最初のステップにすぎません。今後は、ハイドロゲルにさまざまな物質(例えば、創傷の消毒に使われる化学物質)を組み込むなど、バイオフィルムの挑戦は続きます。
Choong教授は、バイオフィルムを直接検査する抗生物質感受性検査(AST)を開発することで、より少ない抗生物質と適切な抗生物質を用いて患者により良い治療法を提供し、抗生物質の過剰処方や過少処方を防ぐことを目指しています。この新しいアプローチによるメリットを受けられるのは患者だけではありません。物質をゲルに固定化することで、病院内で飛散やエアロゾル化する可能性のある危険な液体の使用を最小限に抑え、病院スタッフにもより安全な環境を提供することができるようになります。
将来的には、抗生物質をハイドロゲルに含ませ、ASTに細菌を植え付けるまでの全工程をバイオプリンティングで可能にしたい、と研究チームは考えています。
微生物学研究におけるバイオプリンティングの導入: 勧める理由と期待される可能性
「使うのが楽しみな技術です。探求したいことがあり過ぎる!ある分野から別の分野へ技術を連携させるのが大好きなAIMESの私たちにとって、研究を発展させるエキサイティングな方法です。新しい技術を使うことで、自分の仕事における疑問に対して日々最良な回答が見つかります。また、新たな疑問も常に生まれるので、新しく刺激的な研究が生み出されていくのです。」